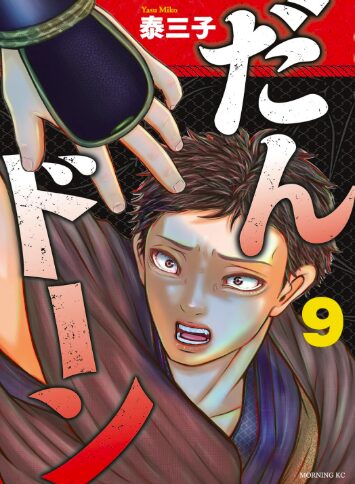このサイトはアフィリエイト広告を利用しております
『だんドーン(9)』レビュー|京に天誅ブーム到来!多賀者との最終決戦を徹底解説
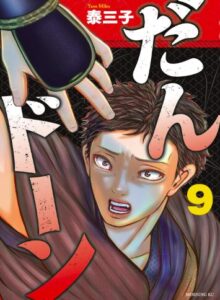
『だんドーン』第9巻は、京の都に“天誅ブーム”が吹き荒れる幕末の狂騒を描く、シリーズ中でも屈指の緊迫回。薩摩と長州がそれぞれの理想を掲げ、中村半次郎・田中新兵衛・岡田以蔵といった“人斬り志士”たちが暗躍する中、ついに宿敵「多賀者」との因縁が決着を迎える。混沌と狂気が支配する中で、人々が信じた“正義”はいつしか暴力へと変わっていく――。長州動乱を描く特別編「奇傑の狂想曲」も収録され、笑いと血煙が交錯する山田芳裕流・幕末群像劇の真骨頂がここに。
作品概要/第9巻あらすじ
『だんドーン』は、幕末の動乱期を舞台に、薩摩や長州など志士たちが「天誅」と呼ばれる暗殺劇を繰り広げる社会派コメディ。
作者は山田芳裕氏。『へうげもの』で知られる彼らしい歴史×風刺のセンスが光る作品です。
第9巻では、京の都に「天誅ブーム」が到来。世の中が混乱の極みに達する中、薩摩・長州両藩の思惑が交錯し、京都はまさに血と理想が入り混じる修羅場と化します。
物語の中心となるのは、薩摩の中村半次郎、田中新兵衛、そして岡田以蔵といった“人斬り”たち。
彼らがそれぞれの信念を胸に暗躍する一方、長年の因縁を抱える「多賀者(たかもの)」との決着が迫ります。
さらに特別編「奇傑の狂想曲」では、長州藩の動乱を描写。
時代を越えて語られる「維新前夜の熱狂」が、壮大かつ痛烈な筆致で描かれています。
幕末を生きた人間たちの“正義”と“狂気”が交錯する、シリーズ屈指の激動回です。
登場人物と勢力関係の変化
第9巻では、主要キャラクターたちの思想と関係性が一気に変化します。
まず中心となるのは、薩摩藩の剣客 中村半次郎(後の桐野利秋)。
冷静で理性的ながらも、時に感情に突き動かされる姿が描かれ、彼の“革命家としての萌芽”が見え始めます。
一方、田中新兵衛や岡田以蔵といった“人斬り志士”たちは、己の正義と狂気の境界で揺れ動く。
「天誅」という名のもとに殺人を正当化する彼らの心理には、時代に押し潰される若者たちの儚さが滲みます。
対するは、薩摩の因縁深い存在「多賀者」。
彼らは一見、敵として立ちはだかるが、時代の流れに翻弄された悲劇的な立場でもあります。
この対立構造の中で、誰が正義で誰が悪か——その線引きは曖昧で、作品全体に深い余韻を残します。
さらに特筆すべきは、後の「日本警察の父」川路利良の登場。
冷静沈着な青年として描かれ、のちに秩序と統制の象徴となる彼の原点が垣間見える。
第9巻は、幕末という群像の中で“理念が形を変えていく瞬間”を見事に描いた巻です。
天誅ブームと暗殺者たちの葛藤
この巻の最大のテーマは、“天誅ブーム”という時代現象そのもの。
「国を救う」「不義を正す」といった大義名分のもとに、暗殺が流行のように広がる京都。
しかし、その裏には正義と狂気の表裏一体の構図が潜んでいます。
中村半次郎たちは理想のために刀を振るうが、次第にその理想が空洞化していく。
彼らの行動は次第に民衆の娯楽や恐怖の対象となり、天誅が「暴力の祭り」へと変質していく。
その空気の中で彼らは、自分たちの行いの意味を見失い始めるのです。
作者・山田芳裕氏はこの現象を痛烈に風刺。
彼の描く“天誅ブーム”は、幕末の実話を下敷きにしながらも、現代社会への鋭い比喩となっています。
正義の名を借りた暴力がいかに人々を熱狂させ、同時に破滅へ導くか。
笑いと恐怖の中に社会批評を織り交ぜる手腕は、本作ならではの魅力です。
幕末史との対比・史実考察
『だんドーン』第9巻は、フィクションながらも史実へのリスペクトが非常に強い作品です。
登場する中村半次郎、岡田以蔵、田中新兵衛といった人物は、いずれも実在した“幕末の志士”たち。
彼らは倒幕運動や尊王攘夷思想のもと、「天誅」を掲げて暗殺を行ったことで知られています。
作中では、これらの史実を背景に、彼らの行動が“義”と“狂”のどちらに傾いていたのかを丹念に描写。
例えば、岡田以蔵の迷いと暴走は、史実における「以蔵の転落」を想起させ、彼の悲劇性を際立たせています。
また、中村半次郎の描写は史実よりも“知性”と“組織戦略”に焦点を当てており、後に西郷隆盛の片腕として活躍する「桐野利秋」の片鱗が見えます。
さらに、川路利良の登場は、史実的にも興味深い。
幕末期の混乱を経て、のちに警察制度を築く彼が“天誅ブームの終焉”を象徴する存在として描かれているのです。
つまり第9巻は、史実を再構成しつつ「暴力から秩序への転換」という歴史の節目を象徴的に示していると言えるでしょう。
作画・演出分析 ― 混沌と緊張の美学
本巻では、作画の緻密さと演出の巧みさが際立っています。
特に京の町を舞台にした天誅シーンは圧巻で、夜の闇と提灯の光、そして刀光の対比が見事。
山田芳裕氏の筆致は、戦闘のスピード感と静けさを同時に描き出し、「斬る」瞬間の重みを感じさせます。
また、人物表情の描写も秀逸。
半次郎の冷静な瞳、新兵衛の焦燥、以蔵の狂気と涙――それぞれの顔に宿る感情の振れ幅が、台詞以上の迫力を生んでいます。
ページのコントラストも印象的で、墨絵のような陰影表現が物語の“死と再生”というテーマを際立たせます。
特別編「奇傑の狂想曲」では、画面の密度と構図がさらに研ぎ澄まされ、長州藩の混乱がまるで楽譜のようにリズミカルに展開。
戦いの悲壮さを“音”として読者に感じさせる構成は、まさにタイトル通り“狂想曲”のような完成度です。
テーマ考察 ― 正義と暴力の境界線
『だんドーン』第9巻が描く中心テーマは、「正義と暴力の境界」です。
天誅を掲げる志士たちは、自らを「正義の代行者」と信じて行動します。
しかし、殺害という手段を繰り返すうちに、彼らの中から“正義”の意味が消え、暴力の快楽と自己正当化だけが残っていく。
この構造こそ、山田芳裕作品に一貫する“人間の愚かさと希望”の縮図です。
天誅ブームは、群衆が「誰かを断罪したい」という衝動に駆られる集団心理の象徴でもあります。
つまり本作は幕末を題材にしながら、現代社会の「正義中毒」「断罪文化」への風刺を含んでいるのです。
その中で中村半次郎や川路利良といった“秩序を取り戻す者”が対比的に描かれ、
暴力の終焉と理性の夜明けを象徴します。
このように第9巻は、幕末という時代の悲劇を超えて、
「人はなぜ正義を信じ、なぜその正義で人を傷つけるのか」という普遍的な問いを突きつけています。
読者反響・SNSレビュー分析
『だんドーン』第9巻は発売直後からSNS上で大きな反響を呼び、
「幕末の狂気と笑いがここまで両立する漫画は他にない」と話題になりました。
特にX(旧Twitter)やレビューサイトでは、
「天誅ブームの描写が現代社会の“炎上文化”と重なってゾッとした」
「中村半次郎の静かな狂気が怖いほど美しい」
「史実を下敷きにしながら、ちゃんとエンタメしてるのがすごい」
といったコメントが目立ちます。
また、特別編「奇傑の狂想曲」への評価も高く、
「短編なのに濃密」「長州藩の動乱が一話完結で見事にまとめられている」との声も多数。
一方で、「以蔵の出番が少なく寂しい」「コメディ要素が控えめ」といった感想も見られましたが、
全体的には“シリーズ中盤の傑作”として位置づけられています。
読者の間では、「天誅=暴力の連鎖」というテーマが議論を呼び、
「山田芳裕はいつも時代を通して“人間の愚かさ”を描いている」という意見も多く見受けられます。
シリーズ内での位置づけ・展開評価
『だんドーン』第9巻は、シリーズ全体の中で「天誅編のクライマックス」といえる位置づけにあります。
第8巻までで描かれた幕末の理想主義が、ここで一気に瓦解し、
人々の正義が暴走する“転換点”となるのがこの巻です。
物語構造的には、
-
京での天誅ブーム=カオスの極致
-
多賀者との決着=因縁の終焉
-
川路利良登場=新時代の幕開け
という三層構成で描かれており、幕末の終末と明治への胎動を見事に接続しています。
また、第9巻ではこれまでの“ギャグ×シリアス”のバランスが変化し、
笑いよりも思想・社会批評の比重が増しているのが特徴。
これはシリーズ全体のテーマが「歴史風刺」から「人間と国家の関係」へと進化していることを示しています。
次巻以降の焦点は、暴力の後に訪れる“秩序の創出”――すなわち川路利良による新しい体制の始まりへと移行していくでしょう。
まとめ/第9巻を読むべき理由
『だんドーン(9)』は、笑いと狂気、史実と虚構が見事に交錯する、シリーズ中でも屈指の完成度を誇る一冊です。
京の天誅ブームを背景に、「正義」と「暴力」の境界を問う物語は、
ただの歴史漫画ではなく、現代社会にも通じる鋭いメッセージを放っています。
また、登場人物たちの心理描写が一段と深まり、
中村半次郎・田中新兵衛・岡田以蔵といった“人斬り志士”たちが、
それぞれの正義に殉じ、時代の波に飲まれていく姿が胸に刺さります。
作画面でも、夜の京都を舞台にした演出の美しさ、
静と動の対比、墨絵のようなコントラストが圧倒的。
さらに、長州藩を描く特別編「奇傑の狂想曲」も収録され、
物語世界の広がりを感じさせる構成となっています。
『だんドーン(9)』は、
「人間の正義がどこで狂気に変わるのか」を描いた幕末群像劇の白眉。
山田芳裕の筆が放つ風刺と情熱を、ぜひその目で体験してください。