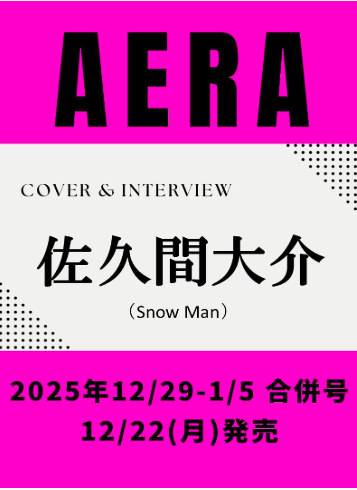このサイトはアフィリエイト広告を利用しております
- AERA 佐久間大介|表紙・撮影・ロングインタビュー完全収録
- 1. 佐久間大介(Snow Man)カバー&ロングインタビュー:2026年、僕が進む道
- 2. 2026年の日本はどうなる?経済・政治・社会を読み解く10の最新予測
- 3. 「叱る」はもう古い?2026年型“やさしい指導”と行動科学が示す新常識
- 4. 女性×働く:2026年のキャリア・制度・働き方の未来図
- 5. 姜尚中 × 東浩紀【eyes特別対談】2026年の世界とAI社会をどう読むか
- 6. 佐藤優の実践ニュース塾:国際政治の行方と2026年の核心
- 7. 田内学の“経済のミカタ”:インフレ時代の家計戦略2026【完全ガイド】
- 8. 武田砂鉄「今週のわだかまり」:分断と孤独社会をどう読み解くか
- 9. ジェーン・スーが語る2026年の人間関係:SNS疲れと“ちょうどいい距離感”
- 10. 共働き夫婦のリアル2026:家事負担データで読み解く「はたらく夫婦カンケイ」最新事情
- 📘 AERA合併号まとめ
- ✨ 一言でまとめると…
AERA 佐久間大介|表紙・撮影・ロングインタビュー完全収録

AERA合併号の表紙を飾るのは、今もっとも輝きを放つ存在の一人、Snow Man・佐久間大介。蜷川実花の鮮烈な色彩に包まれながら、2026年へ向けた思いと、表現者としての変化を語った。挑戦を恐れず、自分の可能性をひらくために進み続ける——その姿勢は、混迷の時代を生きる私たちに大きな示唆を与えてくれる。本号では、ロングインタビューに加え、経済・国際情勢・働き方・人間関係など、2026年の日本を読み解く多角的な特集を収録。変化の年を迎える今、未来へのヒントを詰め込んだ一冊だ。
1. 佐久間大介(Snow Man)カバー&ロングインタビュー:2026年、僕が進む道
2025年の活動を駆け抜け、2026年の扉を開けようとしている佐久間大介。蜷川実花の鮮烈な色彩に包まれながら、彼は“今の自分”と“これからの自分”を静かに語り始めた。
「挑戦する場所があるなら迷わず行きたい。背伸びじゃなくて、自然にステップを上げていく感覚が好きなんです」。そう語る彼の表情は軽やかだが、その裏には確かな覚悟がある。
ダンス、歌、バラエティ、声優、アニメ——ジャンルの境界線を軽く飛び越えてきた2024〜2025年。だが本人は「守りに入るのは性に合わない。2026年は“もう一段階、自分を更新する”年にしたい」と話す。
蜷川実花のレンズに映る佐久間大介は、鮮やかで、柔らかくて、しかしどこか強い。
“変わっていくこと”を恐れずに前へ進もうとする姿が、この2026年の象徴なのかもしれない。
2. 2026年の日本はどうなる?経済・政治・社会を読み解く10の最新予測
2026年の日本は、経済・政治・社会のあらゆる面で変化が加速する一年となる。
専門家分析と最新データをもとに、未来を読み解く10の視点が浮かび上がった。
まず経済。賃上げの流れは続くものの、物価と賃金のバランスは不安定で、家計は引き続きインフレの影響を受ける。他方で、企業の投資はAI・自動化へ大きくシフトし、ホワイトカラーの仕事が再定義される転換期だ。
政治面では、米大統領選の影響とアジア太平洋情勢が日本の外交方針を揺らす。防衛費増額や経済安保は避けて通れないテーマになる。
社会面では、教育のデジタル転換、SNS疲れ、孤独問題の深刻化が課題となる。
「未来を悲観する必要はないが、構造変化を理解する力は欠かせない」と専門家は語る。
2026年、日本は“変化にどう向き合うか”が問われる一年となる。
3. 「叱る」はもう古い?2026年型“やさしい指導”と行動科学が示す新常識
「叱る」文化は長く続いてきた。しかし行動科学の研究が進む中で、その有効性には疑問符がつき始めた。2026年、コミュニケーションの常識は大きく変わろうとしている。
叱る行為は、短期的には行動改善が見られる。しかし長期的には信頼関係を損ない、パフォーマンスの低下を招く可能性が高いことが分かってきた。
代わりに注目されているのが「やさしい指導」。
これは“甘やかす”ことではなく、
・行動の客観的フィードバック
・改善点の共有
・感情的圧力を排除した対話
を基本とした科学的コミュニケーションだ。
企業のマネジメント改革でも導入が進み、離職率や職場ハラスメントの改善につながっている。
2026年、必要なのは“強さ”ではなく“丁寧さ”。対話の質を高めることで、個人も組織も成長する時代に入っている。
4. 女性×働く:2026年のキャリア・制度・働き方の未来図
2026年、女性の働き方は新しいステージに入る。
リスキリング、副業解禁、柔軟な勤務制度、企業の採用方針の変化……キャリアの選択肢は大きく広がる。
今後のポイントは「複線化」。
1つの会社で昇進する伝統型キャリアから、自分のスキルや価値観を軸にした“流動型キャリア”へと移行していく。
また、ジェンダー賃金差の見える化や、育児・介護支援制度の拡充など、女性が働きやすい環境整備も進む。一方で、家庭内の負担格差や管理職比率など、解決すべき課題は残る。
専門家はこう指摘する。
「制度は整いつつある。次に必要なのは“使いやすい文化”だ」。
2026年、女性の働き方改革は“実装フェーズ”へと進む。
5. 姜尚中 × 東浩紀【eyes特別対談】2026年の世界とAI社会をどう読むか
AERAの人気連載「eyes」に登場する姜尚中と東浩紀。思想と社会分析の第一人者である2人が、2026年の世界とAI社会の行方を深く語り合った。
姜氏は語る。「世界は今、構造的な分断を抱えている。米中対立、戦争の長期化、経済格差。これらは短期で解決しない問題だ」。
東氏は続ける。「AI社会は便利だが、選択肢が増えるほど人は疲れていく。情報の洪水が“考える余裕”を奪っている」。
2人が共通して指摘したのは、「社会が急激に変わる中で、個人の思考が追い付かない」という現実だ。
では、これからの社会をどう生きるべきか。
姜氏は「事実を問い直す力」、東氏は「思考の時間を取り戻すこと」が重要だと語る。
2026年は“不確実性の時代に思考する力”が問われる一年になる。
6. 佐藤優の実践ニュース塾:国際政治の行方と2026年の核心
元外交官で作家の佐藤優は、国際ニュースを読むうえで「2026年は分岐点になる」と語る。
世界は今、表面上は個別の出来事に見えても、深層では“同じ構造変化”が進んでいる。
まず、米大統領選後のアメリカだ。内政・外交の優先順位が揺れ、国際秩序の軸が不安定化する。「アメリカの迷走は、同盟国の日本にも確実に影響する」と佐藤氏は言う。
中国は経済減速の中でも強気の外交姿勢を崩さない。アジア太平洋の緊張は高まり、台湾情勢は引き続き重要なリスク要因だ。
さらに、ロシア・ウクライナ戦争の長期化、エネルギー市場の揺らぎ、中東の不安定化など、世界の焦点は分散しているように見える。しかし佐藤氏は「これらには共通した“地政学の再編”という流れがある」と解説する。
国際ニュースは点で捉えると誤る。
国家の戦略、歴史、地政学、経済が交差する“線”として理解することが、2026年の世界を読む鍵だ。
7. 田内学の“経済のミカタ”:インフレ時代の家計戦略2026【完全ガイド】
インフレが長引く2026年、「家計を守る知識」はもはや必須だ。経済学者の田内学は、複雑化する経済環境において「数字を見る力」と「仕組みで家計を守る発想」が重要だと語る。
まず最優先は 固定費の見直し。
サブスク、通信費、保険料の最適化は即効性が高い。住宅ローンにも注意が必要で、金利上昇時代には「無関心が最大のリスク」になる。
次に重要なのは 預金だけでは資産が減る時代 に入っているという認識だ。インフレ率が2〜4%で推移する中、普通預金の実質価値は年々目減りする。
「投資=難しい、怖い」ではなく、「投資=インフレ対策の一部」という発想が必要だと田内氏は強調する。
加えて、2026年は税制改正や企業の賃上げ方針など、家計への影響が大きい政策が続く。国の動きを押さえることも欠かせない。
「節約ではなく“構造理解”で家計は強くなる」。
田内氏の言葉は、変化の時代を賢く生きるための指針になる。
8. 武田砂鉄「今週のわだかまり」:分断と孤独社会をどう読み解くか
日常の違和感を鋭く掬い取る武田砂鉄。2026年の社会には、「分断」と「孤独」というキーワードがより色濃く現れていると指摘する。
SNSでは“正しい言葉”の奪い合いが続き、人々の会話は賛成か反対かの二項対立に収束しがちだ。そこにあるのは、「複雑さへの耐性」が失われつつある現実だ。
武田氏は言う。「私たちは、相手の背景を想像するより、瞬時に判断することを求められる社会に生きてしまっている」。
スピードが価値とされる現代において、丁寧な対話はむしろ“贅沢な行為”になりつつあるのかもしれない。
また、孤独の問題も深刻だ。多様性が叫ばれるほど、逆に“正しさの監視”が強まり、人々はふとした瞬間に孤立する。
武田氏は「社会に“余白”を戻すことが必要だ」と語る。
白黒つけることを急ぎすぎず、曖昧さを許す。
その小さな態度の積み重ねが、分断社会をほぐすヒントになる。
9. ジェーン・スーが語る2026年の人間関係:SNS疲れと“ちょうどいい距離感”
ジェーン・スーは、2026年の人間関係をこう表現する。「“つながり疲れ”と“孤独”の間で、人は揺れている時代」。
SNSは便利だが、承認や比較のステージにもなる。スー氏の取材では、「SNSを開けば疲れる」「誰かの期待に応え続けてしまう」という声は少なくない。
そこで注目されるのが “ちょうどいい距離感” の取り方だ。
・無理に繋がらない
・自分のペースで返信する
・関係性を“選び直す”
こうした姿勢が2026年の人間関係のスタンダードになりつつある。
一方で、対面コミュニケーションの価値もあらためて見直されている。「本当に深い関係は、少ない方がいい」とスー氏。
“広く浅く”から“少なく深く”へ——
デジタル時代を生きる私たちは、ようやくその選択ができるようになってきた。
10. 共働き夫婦のリアル2026:家事負担データで読み解く「はたらく夫婦カンケイ」最新事情
共働き世帯は増え続け、今や日本の標準モデルだ。しかし2026年の最新データでも、家事・育児の負担は依然として女性に偏っている。
「妻の家事負担は夫の2倍以上」——この構造は根深い。
本特集では、家事分担表を導入して改善した夫婦のケースや、仕事・育児を“プロジェクト化”する取り組みを紹介。
負担の公平性よりも「納得感」が大事だという研究結果は示唆に富む。
企業の取り組みも進み、男性育休の取得率は上昇した。しかし、制度があっても使いにくい文化が残る企業も多く、“制度と現場のギャップ”は依然大きい。
2026年、夫婦のあり方は「二人でつくるチーム」へと進化しつつある。
家事の見える化、対話の習慣、データの活用——それらはすべて、家族をより持続可能な形にするための実践だ。
📘 AERA合併号まとめ
本号は、2026年という転換点を前に、日本と世界、そして私たち一人ひとりの“これから”を多角的に描いた特集です。
まず、表紙を飾る 佐久間大介(Snow Man) のロングインタビューでは、挑戦を続ける姿勢と、2026年へ向けた前向きな視線を紹介。
蜷川実花の色彩美と重なり、変化の時代を進む力強さが浮かび上がります。
続く特集では、
経済・政治・国際情勢・社会問題・心理・家計・働き方・夫婦関係など、
多くの専門家の視点から「2026年に何が起きるのか」を読み解きました。
-
インフレの影響はどう続く?
-
米中対立や国際情勢はどう変わる?
-
女性のキャリアや働き方はどう進化する?
-
SNS疲れや孤独はどう解消できる?
-
共働き夫婦の課題はどうすれば改善できる?
こうした“生活に直結するテーマ”を、実データと具体例を交えて整理しています。
どの記事にも共通しているキーワードは、
「変化の時代をどう生きるか」 という視点です。
専門家たちは、不確実な未来を悲観するのではなく、
変わり続ける社会を理解し、自分の人生を主体的に選ぶ時代が始まっていると語ります。
✨ 一言でまとめると…
2026年は、社会も人も“変わらざるを得ない年”。
だからこそ、変化を恐れず、しなやかに進んでいくことが大切だ。
本号は、そのための“未来の地図”のような一冊です。